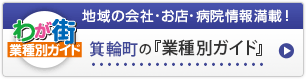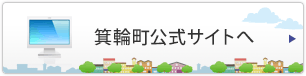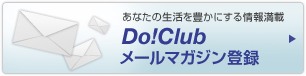箕輪町特集
[長野県]
箕輪町は県のほぼ中央部、上伊那郡の北部に位置し、河岸段丘の典型的な地勢を示しています。中部平坦地を北から南へ天竜川が貫流し、竜東は狭小な台地から伊那山脈に、竜西は広い緩傾斜の台地となって中央アルプス連峰に続き、ともに農耕地帯を形成しています。
周囲は、東に山林をもって諏訪市・伊那市高遠町に接し、南は耕地・原野をもって伊那市・南箕輪村に連なり、西北は耕地・山林をもって辰野町に接しています。また、一級河川として西に桑沢川・深沢川・帯無川、東に沢川等があり、いずれも天竜川に合流しています。
平坦部をほぼ南北に、幹線道路(国道153号・主要地方道伊那辰野停車場線・県道与地辰野線・主要地方道伊那箕輪線・町道1号線・国道153号バイパス・中央自動車道西宮線)が走り、これらを結んで多数の主要町道等が走っています。JR飯田線も中部平坦地を天竜川に沿って南北に走り、町内に伊那松島・木ノ下・沢の3駅があります。
箕輪町のいいトコ!!
箕輪町で憩い・楽しむ
みのわテラス
雄大なアルプスを一望できる、町のランドマークです。地元の食材にこだわったレストラン、新鮮な野菜が手に入る農産物直売所、シーズンフレーバーのソフトクリーム等が楽しめるスタンド、レンタサイクルなど、“美味しい”“楽しい”を通じて、子どもから大人まで楽しめます。
| 関連サイト | https://www.minowaterrace.jp/ |
|---|

箕輪ダム・もみじ湖
ダムによって造られた湖は通称「もみじ湖」と呼ばれ、湖畔一帯には約1万本のもみじが植えられています。感動の情景を求めシーズン中は多くの人で賑わいます。

萱野(かやの)高原
伊那谷を一望することができ、 山頂には遊歩道が整備されています。展望台からは、140度の大パノラマが広がり、信州のサンセットポイント100選に選ばれています。
| 所在地 | 三日町2290 |
|---|

箕輪町の名所・文化
吉田人形芝居
江戸時代中期より上古田に伝えられる人形操りです。現在は保存会、中学校のクラブ等により活動が続けられています。

長岡神社本殿
元は八幡宮と称し、長岡地区の産土神(うぶすながみ)として尊崇されてきました。現在の本殿は、享和元(1801)年に完成しました。

中曽根の獅子舞
今から約200年前の文化文政年間に始まったとされています。家内安全と五穀豊穣を祈願した、その勇壮な舞は、中曽根獅子舞保存会によって守り続けられています。

箕輪町の特産・名物
赤そば
箕輪町上古田・標高900メートルの高原に、4.2ヘクタールの広大な赤そば畑が広がっています。赤そばは花が美しいだけではなく、風味豊かで、コシが強いのが特徴です。

まつぶさ
モクレン科マツブサ属の落葉性つる植物です。つる性の樹皮は、ごつごつとしたコルク状で、削ると松脂の匂いがします。また実がブドウの房に似ていることからまつぶさ(松房)という名前がつきました。
抗酸化成分が豊富に含まれていることが知られており、近年、その機能性に注目が集まっています。

杜仲茶
1981(昭和56)年、漢方薬木杜仲の葉を原料にした杜仲葉加工茶が富山医科薬科大学和漢薬研究所長・難波教授(当時)の協力を得て箕輪町で産声をあげてから34年。杜仲茶は全国ブランドとして定着し本場中国にまで広がっています。